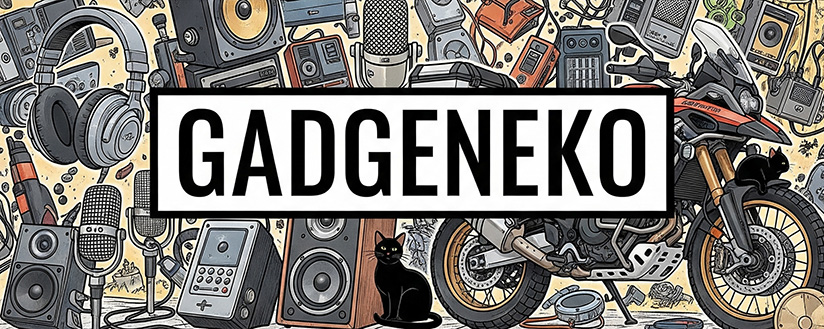当ブログではおなじみの、上記デカい蜂みたいなバイク。
今年で8歳となり、相応の愛着が持てる相棒となっている。
以下の記事で確認できるほぼデフォ状態の頃と比べると色々と変化が見れて面白い。
本バイクに対する不満はほぼなく、自分の使い方に大変に合致した優秀なバイクと評価している。
Vツインエンジンは鼓動が良くパワフル、低回転時のトルクフルな立ち上がりは他の追随を許さない熟成具合があるうえ、垂直安定性も大変に良好。
ガソリンはレギュラー指定だし上手く走れば1㍑28kmで走ってくれたりする。
クッションはふかふかであるし、着座姿勢も無理がなく、長距離ツーリングも楽々。
うーむ、パーフェクトだ。
ただ一つ不満な点を挙げるのであれば、重箱の隅をつつく様なことではあるのだけども、足が垂直に降ろされること。
大多数のバイクがそうだろうと、スポーツタイプに至ってはもっと折り曲げる形での着座姿勢だろうと、ないってんだお前、という話なのは重々承知。
それでもより快適な環境を構築したくなるのは、ガジェオタの性というものだろう?
ということで色々とやってみよう。
なお本記事はお察しの通り、以下試行錯誤シリーズ同様に順次更新される記事となる。
バイクの着座姿勢について

上記画像のように、バイクの車種によって着座姿勢は千差万別となる。
スポーツタイプはより鋭角に膝が曲がり、クルーザータイプに近づくにつれその角度は開いていくことになる。
ハーレーなどのアメリカンでは、足を投げ出すように前に配置することになる。
これはアメリカ大陸という超クソデカマップを走破するために最適化された形状であり、足を曲げないように配置する=負担が少ないという証明にほかならない。
じゃあオイラのバイクにもそういう足場作ろうぜ、というのが今回の計画になる。
日本国内でそういう事やっている人を微塵も見かけないが、アルペンツアラーが盛り上がっているヨーロッパではそのようなカスタムを多く見かけることができる。
実例を挙げることができないのが申し訳ないが、筆者の記憶ではイタリア・ミラノで行われている世界最大規模のバイクショー「EICMA」の2020年とかでポピュラーなカスタムの印象があった。
その記憶があったので筆者もやってみようと思ったのが今回の計画の発端となる。
第1回計画
プレートで装着

揃えたのは上記アイテム。
筆者は溶接とか鉄加工はできないので、まずは簡易なものでそれっぽくやってみようと。
ネジやボルトは適当に。ワッシャーは不要ではあるが、緩み防止にあったほうが吉。
ステーも自分の足の長さに合わせて適当で良いが、ステンレスなどの錆に強い素材であること、調節のためにネジ穴が多く設けられているモノを選ぶとよいだろう。
ということで選ばれたのは以下。
これらをいい感じにくっつける。
重量の配置や全体の歪み等を意識して組み合わせると以下のような感じに。



如何にもプロトタイプって感じでいいじゃないか。
この雑味がいいんだよな。なぁ男子諸君。
Deepaの可倒式ステップもコンパクトに纏めることが出来ていい感じ。
使わない時は折り畳めるし、バイクが転倒したとしても折りたたまれることになるので致命的な機能不全につながることはないだろう。



装着するとこんな感じ。
スズキ純正アクセサリーバーに装着してみると筆者の足の長さにステーが足らず、結局もう1セット購入して繋げる羽目になってしまった。
足が長くてごめんね!
全体が黒なので謎突起として違和感はありつつも、目立つこともなく馴染んではいる。
この雑多な感じが許されるのがアドベンチャーバイクのいいところでもある。
実用性
正直満足度は高い。
足を投げ出す形で置くことができるので、長距離の高速道路移動が格段に楽になった。
ただし、プレート故にしなってしまう。
バイクのはずみでぼよんぼよんするし、走行中にもげたりしないかという不安感がすごい。
1枚だからしなってしまうという話なのならば2枚重ねてみたらどうか、という説もあるが、恐らくソレだけで片側のみで1kgを超えるヘビー級なカスタムになってしまう。
そうなると自重とバイクの振動で配置がズレたりするわけで、更に足を乗せるとその重さでよりズレるわけで…と現実的ではない。
目的の快適性は確保できたが安定性が無く、安心して使用できる環境ではない、という印象。
やはりスチールパイプ(or鉄パイプ)を溶接しかないのか…
現状

ということで、現状はまだ第1回計画のプレート固定方式で運用中。
目的は果たせてはいるものの、正直この運用は不安感が強く、いつ何が起きてもおかしくないという状況となる。
早急に改善した環境を構築したくはあるが、いかんせん金属加工技術が無いので採用案が絞られてしまう。
さて、どうしたものか。
足らぬ足らぬは工夫が足らぬ。
ということで未来の筆者の想像力に期待してみよう。
試作の結果が更新され次第、本記事に反映していく予定。